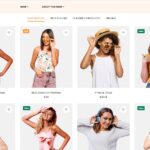TypeScript実践

TypeScriptとJavaScriptの違い
TypeScriptにはJavaScriptにはない機能がいくつか提供されていますが、なかでも大きな違いとしては以下の3つになります。
①静的型付けによる定義
②インターフェースの活用
③モダンなJavaScriptが使える
「①静的型付け」は、簡単に言うと変数が扱うデータが文字列型なのか数値型なのか……など、あらかじめ型を定義することで、意図しないデータが混入するのを防ぐことができます。
「②インターフェース」は、プロパティや型をあらかじめ定義しておくことで安全にクラスを作成できる機能を提供します。
そして、「③モダンなJavaScript」が使えるという点においてもTypeScriptは優れています。どういうことかと言うと、TypeScriptはコンパイルすると素のJavaScriptに変換されるのです。この変換されたJavaScriptはどのブラウザでも使える状態になっているので、最新の仕様をいち早く利用できるわけです。
これらの大きな違いについて、まずは概要だけ先に確認しておいてください。
①静的型付け
JavaScriptは型の定義ができない
まず最初に、なぜ「静的型付け」を使ったほうがいいのかについてを解説するために、JavaScriptの簡単な例を見てみましょう。
以下のサンプルコードは、任意の文字列を受け取ってメッセージを返す関数です。
const message = name => {
console.log(`こんにちは${name}さん!`);
}この関数は、引数として文字列を受け取ることが前提になっています。
しかし、JavaScriptには「静的型付け」ができないので、「この関数は文字列を受け取らないといけない……」と開発者が自分で言い聞かせる必要があります。
そのため、例えば以下のように誤って引数に数値を指定しても特にエラーは起きません。
message(1234);実行結果
こんにちは1234さん!エラーが発生しないので、JavaScriptではさらに複雑なロジックを組み立てて検出できるように実装します。しかし、最悪のケースだとこのままエラーに気づかずに、正式にリリースされてしまうこともあるわけです。
今回のサンプル例はメッセージを出力するだけですが、重要なロジックで型が定義されていないとバグを引き起こすことは簡単に想像がつきます。このようなJavaScriptの弱点を解消するために、TypeScriptでは「静的型付け」が採用されているわけです。
変数の型
それでは、TypeScriptによる「静的型付け」がどのようなものか、具体的なコードと一緒に解説をしていきます。
まずは、もっとも基本になるTypeScriptの変数定義を見てみましょう。
変数を定義する方法はJavaScriptと基本的には同じなのですが、あらかじめ型を定義できるように設計されています。例えば、文字列を扱うための変数として「userName」を定義すると以下のようになります。
let userName:string;上記のように変数名のあとに「:(コロン)」を付与してから型を記述します。今回の例だと文字列を扱う変数を作成するので、型は「string」になるわけです。
もちろん、型を定義すると同時に値を以下のように定義することも可能です。
let userName:string = '太郎';このように、型をあらかじめ定義することを「静的型付け」と言います。
変数「userName」は文字列だけを扱うので、誤って数値などが代入されるとTypeScriptをコンパイルするときにしっかりとエラーが出力されます。これにより、変数が扱う型を保証できるのでコードの安全性が飛躍的に向上するわけです。
ちなみに、変数以外にも例えば配列でも以下のように型を定義できます。
const numberList: number[] = [1,2,3,4,5];この例だと、数値のみしか格納できない配列要素を作成できるというわけです。
関数の型
「静的型付け」は変数だけでなく、関数を定義する際にも有効活用できます。
TypeScriptでは、主に「引数」と「戻り値」に型を定義できるように設計されています。例えば、文字列の引数を受け取ることが前提の関数は、以下のように記述できます。
const getName = (userName:string) => {
console.log(userName);
}引数部分に注目してください。
変数を定義するときと同様に、「:」を付与してから型(string)を定義しています。これにより、この関数は引数として文字列だけを受け付けるわけです。
次に、戻り値の型を定義する場合を見てみましょう。この場合は引数のあとに「:」を付与して型を記述することになります。
const getName = (userName:string):string => {
return name;
}上記の例では、型を「string」にしているので、戻り値は必ず文字列型であることが保証されるわけです。このように「引数」「戻り値」の型を定義できることで、意図したデータを扱えるようになります。
オブジェクトの型
TypeScriptではオブジェクト形式のデータにも「静的型付け」ができます。
使い方としてはオブジェクト名を定義したあと、「:」に続けてオブジェクト形式で型を定義していきます。
const user:{name:string, age:number, area:string} = {
name: '山田 太郎',
age: 28,
area: '東京都'
};型を定義している部分に注目してください。
ポイントは、まったく同じプロパティ名に型を定義している点です。つまり、言い換えれば型を定義したプロパティしか利用できないオブジェクトを作成できるというわけです。
例えば、以下の例を見てください。
const user:{name:string, age:number, area:string} = {
name: '山田 太郎',
age: 28,
};この例では、型を定義している「area」プロパティが使われていないことに注目してください。この場合はコンパイルするとエラーになります。
逆に、型を定義していないプロパティを記述しても同じくエラーになります。つまり、「静的型付け」をしたプロパティのみ利用できることが保証されるのでコードの安全性が高まるわけです。
②インターフェースの活用
クラスの作成
TypeScriptではインターフェースを利用することで、クラスを作成するときに自分だけのルールみたいなものを作れるようになります。
例えば、ユーザーを管理するクラスを作成するときに、「ユーザー名」と「年齢」だけは必ずプロパティとして持っておきたいとします。そのような場合に、以下のようなインターフェースをまずは作成します。
nterface Member {
userName:string;
userAge:number;
}上記の例では、文字列型の「ユーザー名」と数値型の「年齢」を定義しているのが分かります。
このように作成したインターフェースはクラスを作成する時に、「implements」に続けて設定することで使用可能になります。
class User implements Member {
userName:string;
userAge:number;
userArea:string;
userTell:string;
}ポイントはインターフェースで定義したプロパティを、必ず利用しなければいけないという点です。そのため、インターフェースで定義されたプロパティが必ず存在するという保証が得られます。
普通はクラスを自由に作成できるわけですが、あえてルールを作成することで誰もが安心して利用できるクラスを提供できるようになるというメリットがあります。
オブジェクト・関数への応用
インターフェースはクラスを作成するときに便利な機能なのですが、実はさまざまなデータにも応用できるので合わせてご紹介しておきます。
例えば、オブジェクトの「静的型付け」をする際に、型の代わりにインターフェースを適用させることができます。先ほど作成した以下のインターフェースをもう一度チェックしてください。
interface Member {
userName:string;
userAge:number;
}このインターフェース「Member」を、オブジェクトの「静的型付け」に利用すると以下のようになります。
const user:Member = {
userName:'山田 太郎',
userAge: 34
}「:」を付与したあとにインターフェースを適用させています。
定義したプロパティだけしか利用できない点については、通常の「静的型付け」と同じになります。
また、関数の引数にも応用可能です。例えば、3つの引数を受け取る関数を作成するには以下のように記述します。
「:」を付与したあとにインターフェースを適用させています。
定義したプロパティだけしか利用できない点については、通常の「静的型付け」と同じになります。
また、関数の引数にも応用可能です。例えば、3つの引数を受け取る関数を作成するには以下のように記述します。interface UserData{
userName:string;
userAge:number;
userHobby:string;
}
const getUser = (data:UserData) => {
console.log(data);
}上記の例は「UserData」というインターフェースを作成しており、あらかじめ3つの型を定義しているのが分かります。
このインターフェースは関数の引数へ「静的型付け」を行う方法と同じように設定が可能になるのです。つまり、ひとつのインターフェースを適用させるだけで、どんな引数を受け取るかを指定できるわけです。
もちろん関数を利用する際には、定義されている引数をすべて受け取らないとコンパイル時にエラーとなります。
getUser({userName:'太郎', userAge:32, userHobby:'読書'});③モダンなJavaScript対応
JavaScriptは、毎年のように言語自体のアップデートが行われる関係で、すべてのブラウザが最新のJavaScript仕様に対応していないことがよくあります。
最近のモダンなブラウザは対応が早くなっておりますが、一部のマイナーなブラウザであったりスマホ版のブラウザなどは注意が必要になるわけです。
しかし、TypeScriptは冒頭でも少し解説しましたが、最新のJavaScriptを利用していてもコンパイルすることで、旧来のJavaScriptに変換される大きなメリットがあります。つまり、ブラウザ対応などの余計なことに時間を費やす必要がなく、開発に集中できるわけです。
例えば、以下のコードを見てください。
const createText = () => {
const userName:string = '山田太郎';
console.log(`こんにちは、${userName}さん`);
}アロー関数内で変数を定義して、テンプレートリテラルを利用して文字列を出力するコードです。
これをコンパイルすると以下のようなJavaScriptに変換されます。
var createText = function() {
var userName = '山田太郎';
console.log("こんにちは、" + userName + "さん");
}主な変換ポイントは以下のとおりです。
- constがvarに変わる
- アロー関数がfunctionに変わる
- テンプレートリテラルから+演算子に変わる
上記のように、旧来のJavaScriptに変換されるためほぼすべてのブラウザで動作するコードになるわけです。
最新のJavaScript仕様はコードを簡潔に書けるようになっていたり、バグが起きにくい書き方ができたりなど、いろいろメリットも多いのでTypeScriptは近年において注目され続けていると言えるわけです。
TypeScriptの高度な型
TypeScriptでは、型で型を定義することが可能(型プログラミング)
変数に対するGenerics
型における変数のようなもの
型を可変にすることで柔軟な型定義を書ける
Genericsを利用する型を宣言するときの慣習として、T、U、Kの名称を利用する
<T> はT型エイリアスと呼ぶ
interface Box<T = string> { // 関数のデフォルト引数と同じように初期型を定義できる
value: T
}
const box0: Box = {value: 'test'}
const box1: Box<string> = {value: 'test'}
const box2: Box<number> = {value: 1}
const box3: Box<number> = {value: 'test'} // Error一方で、型を絞りたい場合もある
その場合はextendsによる制約を追加すればよい
interface Box<T extends string | number> {
value: T
}
const box1: Box<string> = {value: 'test'}
const box2: Box<number> = {value: 1}
const box3: Box<number> = {value: false} // Error関数の引数に対してGenericsを利用する場合
function boxed<T>(props: T) {
return {value: props}
}
boxed(1)引数をnullableにしたい場合は宣言時にasを付与
const box = boxed(false as boolean | null)
const box2 = boxed<string | null>(null)変数の時と同じようにextendsで制約を追加できる
function boxed<T extends string>(props: T) {
return {value: props}
}
const box = boxed(0) // Error
const box2 = boxed('test')引数の型が明示されていることで関数内部の安全性も上がる
interface Props {
amount: number
}
function boxed<T extends Props>(props: T) {
return {value: props.amount.toFixed} // amountがnumberなのでtoFixedが呼べる
}
const box = boxed({amount: 19})複数のGenericsが出てくる場合
function pick<T, K extends keyof T>(props: T, key: K) {
return props[key] // propsはオブジェクトを想定していて、必ず存在するプロパティ名が保証される
}
const obj = {
name: 'Taro',
amout: 0
}
pick(obj, 'name')
pick(obj, 'name1') // プロパティがないのでErrorClassのGenerics
クラスにGenericsを利用することでコンストラクタの引数に制約を付与できる
class Person<T extends string>{
name: T
constructor(name: T) {
this.name = name
}
}
const person = new Person('test')
// クラスメンバーにIndexed Access Typesを利用した例
class Person<T extends PersonProps>{
name: T['name']
age: T['age']
constructor(props: T) {
this.name = props.name
this.age = props.age
}
}
const person = new Person({name: 'test', age: 1})型を抽出したい場合について
対象の型から特定の型を抽出したい場合について理解するためには、型の定義にもIF文(Conditional Types)が適用できることを知っておく必要がある
部分型として型抽出するinferというシグネチャはCondtional Types内で利用するため
以下はif T は X と互換性のある型であれば ? Y : Z と読み替えるとわかりやすい
T extents X ? Y : Z条件に合致した型を抽出する例
Pick型という組み込みUtility Typesを使うのが一番手っ取り早い
interface User {
name: string
kana: string
gender: 'male' | 'female' | 'other'
}
type UserGender = Pick<User, 'gender'>
// UserGender = { gender: 'male' | 'female' | 'other' }キーの名称だと抽出するのは簡単だけどもう少し抽象化して、stringの型のものを抽出したいとなったら
その場合は以下のように独自で定義したFilter型のようなものを作ってやる
type Filter<T, U> = {
[K in keyof T]: T[K] extends U ? K : never // T[K]と互換性のある型Uと一致する場合はK型を返すのがポイント
}[keyof T] // 内部でK型を返しているので末尾は[keyof T]となる
type stringKeys = Filter<User, string> // 'name' | 'kana' というUnion Typeが抽出できるこれをPick型と組み合わせて使うとstringに一致するものを抽出できる
type strings = Pick<User, stringKeys>これまでは直下の階層の型の抽出だったが、ネストした階層の型を抽出したい場合の例
interface DeepNest {
deep: { nest: { value: string } }
}
interface Properties {
deep: DeepNest
}
type Salvage<T extends DeepNest> = T['deep']['nest']['value'] // extends DeepNestがあるのでIndexed Access表記が使える
type DeepDive<T> = {
[K in keyof T]: T[K] extends DeepNest ? Salvage<T[K]> : never
}[keyof T]
type X = DeepDive<Properties> // X = stringinferも型を抽出できる機能を持つ
Conditional Types(IF文)の中で利用する
なにはともあれ例を見ながら読み解く
greet関数に一致したらそのgreet関数が返す型を返す
function greet() {
return 'String型が返るよ'
}
type Return<T> = T extends (...args: any[]) => infer U ? U : never
type R = Return<typeof greet> // type R = string(...args: any[]) => infer U の部分がConditional Typesに該当する
(..args: any[])は引数を取る関数で、アロー演算子でU型という戻り型を返していると解釈
つまり、Tが関数型と互換があれば、その関数の戻り型を返すというIF文
結果、type Rにはstringが入ってくる
Conditional Typesの中であればinferはどこでも利用できる
以下のサンプルでは戻り型ではなく、引数として利用している
function greet(name: string, age: number) {
return 'Hello ${name} ${kana}'
}
type A1<T> = T extends (..args: [infer U, ...any[]]) => any ? U : never // 第一引数の型を抽出
type X = A1<typeof greet> // type X = string
type A2<T> = T extends (..args: [any, infer U, ...any[]]) => any ? U : never // 第一引数の型を抽出
type Y = A2<typeof greet> // type Y = numberUtility Typesについて
車輪の発明をしないようによくあるパターンは組み込み型として定義されている
(いちいち上述したConditional Typesで独自の定義をしなくて済むようにしている)
従来の組み込みUtility Types
interface User = {
name: string
age?: number | undefined
}・Readonly型:Readonlyを強制
type Hoge = Readonly<User>
{
readonly name: string
readonly age?: number | undefined
}・Partial型:Optionalを強制
type Hoge = Partial<User>
{
name?: string | undefined
age?: number | undefined
}・Required型:Optionalを排除
type Hoge = Partial<User>
{
name: string
age: number
}・Record型:新しいObjectを作る。ただし第一引数がキーになって、第2引数が型
type Hoge = Record<'user', User>
{
user: User
}・Pick型:型の抽出。第一引数が対象の型、第2引数がそのプロパティ
type Hoge = Pick<User, 'name'>
{
name: string
}・Omit型:型の除外。第一引数が対象の型、第2引数がそのプロパティ
type Hoge = Pick<User, 'name'>
{
age?: number | undefined
}新しい組み込みUtility Types
- Exclude型:T型の中からUと互換性がある型を
除き、新しい型を生成
type X = Exclude<"a" | "b"> // "a"が抽出("b"はstringで、"a"と互換性があるので"a"を除外して新しい型として生成)・Extract型:T型の中からUと互換性がある型を残し、新しい型を生成
type X = Extract<"a" | "b"> // "b"が抽出("b"はstringで、"a"と互換性があるので"a"を残して、"b"を抽出して新しい型として生成)・NonNullable型:T型の中からnullとundefinedを除外した新しい型を生成
type X = Nonnullable<string | null | undefined> // string・ReturnType型:T型は関数であること。関数ではない場合はコンパイルエラー。そしてその関数の戻り値の型を返す
type X = ReturnType<() => string> // string
type Y = ReturnType<string> // Error・IstanceType型:コンストラクター関数型のインスタンス型を取得
class C {
a = 0
b = 0
}
type X = InstanceType<typeof C>
const n = {} as X // { a: number, b: number }TypeScriptの型システム
この章は型の互換性について説明されている
型には互換性がある
例えば、値側で推測された型と変数側に定義されている型に互換性がないので代入ができないといったケースがありえる
string型とString Literal Types
詳細な型(String Literal Types)に抽象な型(String型)を代入できない
number型とNumber Literal Typesの関係も同じ
// Errorがでない場合
let s1: 'test' = 'test'
let s2: string = s1
// Errorが出る場合
let s1: string = 'test'
let s2: 'test' = s1any型は何にでもなれるので不適切な型を代入できてしまう危険なもの
let a1: any = false
let a2: string = a1 // booleanなのstringに代入しようとしているがエラーにならないunknownは as で型を決めるまで別の方を代入できない
let u1: unknown = 'test'
let u2: string = unknown // Error
let u3: number = u1 as number // u1の型が決まるので代入できるようになる{}型(オブジェクトリテラル) は特殊
object型として定義した場合は理解しやすいが、{}型にすると理解が難しくなる
let o1: {} = 0 // OK
let o2: {} = '0' // OK
let o3: {} = false // OK
let o4: {} = {} // OK
let o1: object = 0 // Error
let o2: object = '0' // Error
let o3: object = false // Error
let o4: object = {} // OK{}型の中身の理解をするのにkeyofでオブジェクトのプロパティ一覧を取得してみれば良い
K2, K3, K4はプロパティを持っていることがわかる。代入できるということは、プリミティブ型は{}のサブタイプと言える。
type K0 = keyof {} // never
type K1 = keyof { K: 'K'} // 'K'
type K2 = keyof 0 // "toString" | "toFixed" ...
type K3 = keyof '1' // "charAt" | "toString" ...
type K4 = keyof false // "valueOf"{}型の代入は特定のプロパティが異なるとエラー、また、互いに一致するプロパティがないとエラー
let p1 = {p1: 'test'}
let p2 = {p1: 1}
p1 = p2 // Error
let p3 = {p3: 'test'}
let p4 = {p4: 'test'}
p3 = p4 // Error部分的にプロパティが一致している場合は代入する方向によってはOK
let p3 = {p3: 'test'}
let p4 = {p3: 'test', p4: 'test'}
p3 = p4関数にも互換性がある
引数に互換性がない場合はエラー
let fn1 = (a: string) => {}
let fn2 = (a: number) => {}
fn1 = fn2 // Error引数に部分的に一致している場合は引数が多い方へ代入が可能
let fn1 = (a: string) => {}
let fn2 = (b: string, c: number) => {}
fn2 = fn1クラスにも互換性
クラスメンバーが比較対象になる
コンストラクターの引数型は関係ない
class Animal {
feat: number
constructor(name: string) {}
}
class Human {
feat: number
hands: number
constructor(name: string, gender: number) {}
}
let animal: Animal = new Animal(`dog`)
let human: Human = new Human(`taro`, 2)
animal = human宣言空間
TypeScriptにはValue、型、名前空間の3つの宣言空間が存在している
それぞれの空間内で宣言名は重複できない
Value宣言空間
値に対して割り当てられる
const greet = 'test'
function greet() = {} // 同じ認識子であるgreetを定義できないとErrorType宣言空間
Typeを宣言する方法は2つ(interface or type alias)で違いはOpen endedへの準拠(後付できるか)
この違いを抑えておく
type aliasの場合は宣言の重複エラーが発生する
interfaceよりもtype aliasが推奨される理由はOpen endedによって予期せぬ不具合を防ぐためか
// interfaceの場合
interface User {
name: string
}
interface User {
age: number
}
↓定義が上書きされて結合
interface User {
name: string
age: number
}
// type aliasの場合
type User = {
name: string
}
type User = {
age: number
}TypeScriptの型安全
どの言語でもそうだけど如何にバグを生まないようにするかは重要
TypeScriptは型がるためその恩恵を受けやすい(TypeScriptを選ぶ理由の1つになる)
型推論だけでなく、意図的に型を絞り込むことで更にバグを生みにくくすることが期待できる
制約による型安全
TypeScriptでは早期リターンをすることで、型が絞込まれた推論が適用されている
このような型の絞り込みの処理をType Guardやガード節と呼ぶ
ガード節の良くあるパターンは後述
function getFormattedValue(value: null | number) {
if (value === null) return value // value: nullと推論される
return `${value.toFixed(1)} pt` // value: numberと推論される
}引数の型にundefinedは含まれていないが、「?(オプショナル型)」を付与することで
TypeScriptが自動で引数のundefinedを考慮しれくれる
function greet(name?: string) { // TypeScriptは function greet(name: string | undefined) と解釈している
return `Hello ${name.toLowerCase()}`
}これの何が嬉しいかというと実行エラーが事前に気づける(nameがundefinedの場合、toLowerCaseが呼べないのでコケる)
実際にこのコードをVSCodeで記述すると、nameがundefinedである可能性を指摘してくれる
つまり、型のみ論理的にチェックをすることで事前にバグを検知できる
Guard節により型の絞り込みをおこなうことで対処できる
function greet(name?: string) {
if (name === undefined) return 'Hello'
return `Hello ${name.toLowerCase()}`
}デフォルト引数を利用した場合は少し興味深い挙動をする
function getFormattedValue(value: number, unit = 'pt') {
return `${value.toFixed(1)} ${unit.toLowerCase()}`
}VScodeで関数の推論された型をみると
function getFormattedValue(value: string, unit?: string): string
とunitはundefinedの可能性を推論している
undefinedと推論した場合、関数内部のtoLowerCaseが実行できない可能性を考慮してエラーを検知してくれるかと思いきやエラーにならない(greet関数の例)
理由は単純でデフォルト値があるから(はundefinedにならないことを保証している)
もちろん、
getFormattedValue(100, 0)
だとunitの型が違うためエラーとして検知される
オブジェクトの型安全についてはWeak Typeというものがある
定義としてはすべてのプロパティがオプショナルな型なもの
一つでも一致していれば意図したものだと判断してくれる
type User = {
name?: string
age?: number
}
function register(user: User) {}
const maybeUser = {
age: 1,
gender: 'male'
}
register(maybeUser) // 1つでも一致していればエラーでない
const notUser = {
gender: 'male',
graduate: 'Tokyo'
}
register(notUser) // Error一方で、オブジェクトリテラルを直接引数に入れるとエラーになる
Excess Property Checks(過剰なプロパティチェック) と呼ばれるもの
オブジェクトリテラルを直接利用することは実際の開発現場で良くあり(設定値を渡すシーンなど)、存在しないプロパティに対して過剰に検査をするようになっている
register({
age: 1,
name: 'Hoge',
gender: 'male'
})readonlyの使い方は2つ
1つはreadonlyシグネチャを利用する
type State = {
readonly id: number
name: string
}
const state: State = {
id: 1,
name: `hoge`
}
state.id = 2 // Errorもう1つはReadonly型を適用する
type State = {
id: number
name: string
}
const state: Readonly<State> = {
id: 1,
name: `hoge`
}
state.id = 2 // ErrorReadonly型はすべてのプロパティに一括でreadonlyシグネチャを付けているのと同じ
しかし、悲しいかなJavaScriptの振る舞いとしては実際には値が書き換わってしまう
あくまでTypeScript上で安全を得ることができるものである
JavaScript側で書き換わるのを制御したいという場合はObject.freezeを使えば良い
type State = {
id: number
name: string
}
const state: State = {
id: 1,
name: `hoge`
}
const frozenState = Object.freeze(state) // VScode上ではReadonly<State>として推論されている
frozenState.id = 2抽象度による型安全
ダウンキャストは抽象的な型から詳細な型を付与すること
TypeScriptよりもプログラマーの方が型に詳しい時に用いる
よってプログラマーは定義した型に責任を持つ必要がある
const defaultTheme = {
backgroundColor: "orange" as "orange", // literal typesのorangeとして定義
borderColor: "red" // stringと推論
}
defaultTheme.backgroundColor = "blue" // Error
defaultTheme.borderColor = "blue" // No Errorちなみにダウンキャストは互換性のある型にしか適用できない
“orange”のliteralをbooleanにキャストすることはできない
const defaultTheme = {
backgroundColor: "orange" as false
}アップキャストは抽象度を上げる(詳細から抽象へ)
抽象度を上げれば安全に聞こえるかもしれないが注意は必要
例えば以下のanyにアップキャストしたことで実行時にしかエラーに気づけ無いconst fiction: number = toNumber('1,000') // anyにアップキャストしたので実際にnumberを期待している変数に入れることができてしまう
fiction.toFixed() // Runtime Error発生するインデックスシグネチャ [k: string] はオブジェクトに動的なプロパティを定義したいときに使う
type User = {
name: string
[k: string]: any
}
const userA: User = {
name: 'Taro',
age: 1
}
const x = userA.age // anyとして推論ただし、トップレベルのプロパティに互換性がない場合はコンパイルエラーを引き起こすの注意
nameがstringでnumberと互換性ないと怒っている
type User = {
name: string
[k: string]: number
}
↓Union Typesにすることで回避できる
type User = {
name: string
[k: string]: number | string
}インデックスシグネチャを利用時に値に対して制限加えたい場合
そんな場合は以下のような定義をすると良い
type Nickname = 'hoge' | 'foo' | 'fuga'
type User = {
[k: string]: Nickname
}
const userA: User = {
name: 'hoge'
}
const x = userA.name // Nickname型と推論される
const y = userA.aaa // Nickname型として推論されて、aaaプロパティがないのにエラーにならない↑の変数yはコードとしては危険なのでそれを防ぐためundefinedを追加しておくこと
type User = {
[k: string]: Nickname | undefined
}
const y = userA.aaa // Nickname | undefinedとして推論されるので後続処理でガード入れることを教えることができるインデックスシグネチャを利用時にキーに対して制限加えたい場合
inキーワード を利用する
type Properties = 'age' | 'hight'
type User = {
[K in Properties]: number
}
const userA: User = {
age: 1,
hight: 170
}
const x = userA.ageconstでも別の変数に入れたり、関数の戻りとして返した時は抽象化されてしまう
そこで、const assertionというものがある
readonlyを全体に付与してくれる
別の変数にコピーされても型定義はそのまま
const tuple1 = [1, '2', false] as const // readonly [1, '2', false]
let tuple2 = tuple1
const a = 'a'
let b = a // 通常は変数にコピーされると型が抽象化されてしまう(Widening Literary Types)関数の場合は以下のようになる
function increment() {
const res = { type: 'INCREMENT' }
return res
}
const x = increment() // { type: string }と抽象化されてしまう
function increment2() {
const res = { type: 'INCREMENT' } as const
return res
}
const y = increment2() // { readonly type: 'INCREMENT' }anyを乱発しないことの例
この例からも分かるように型の緩い不要な戻り型はバグの温床になってしまう
function greet(): any {
console.log('Hello')
}
const message = greet()
console.log(message.toUpperCase()) // anyによって型エラーで検知できないNon-null assersionはプログラマー都合で欺かれた定義であり、その場しのぎでしかない
よって使うべきではない
function greet(name?: string) {
console.log(`Hello ${name!.toUpperCase()}`) // nameがundefinedだとエラーだが型から検知できなくなる
}ほぼお目にかかる機会がないがアサーションを重複して付けることができる
よほどのことがない限り利用はしないこと
const myName = 0 as any as string
console.log(myName.toUpperCase()) // 明らかにエラーでるけど型からエラーを検知できない良くあるガードパターン
typeof演算子
function reset(value: number | string) {
const v0 = value // const v0: number | string
if (typeof value === 'number') {
// ここの段階でvalueはnumberのみと推論される
const v1 = value // v1: number
return 0
}
const v2 = value // v2: string
return ''
}プロパティをin演算子で比較すると型が絞り込まれる
function judgeUser(user: UserA | UserB) {
if ('gender' in user) {
const u0 = user // UserA | UserB
}
if ('name' in user) {
const u1 = user // UserA
}
if ('age' in user) {
const u2 = user // UserB
}
}instanceof演算子はtypeofと同じで違いはクラスに対しての話
class Creature {
breathe() {}
}
class Animal extends Creature {
shakeTail() {}
}
class Human extends Creature {
greet() {}
}
function action(creature: Creature | Animal | Human) {
if (creature instanceof Creature) {
const c1 = creature // Creature | Animal | Human
}
if (creature instanceof Animal) {
const c2 = creature // Animal
}
if (creature instanceof Human) {
const c3 = creature // Human
}
}タグ付きUnion Types
switch文によって型の絞り込みができる
しかし、条件があり、比較されるオブジェクトは共通するプロパティを持っていること
また、その型はリテラルタイプであること
function judgeUserType(user: UserA | UserB) {
switch(user.gender) {
case 'male':
const u0 = user // UserA
return u0
case 'female':
const u1 = user // UserB
return u1
default:
const u2 = user // never defaultブロックに到達するこてゃないため
return u2
}
}TypeScriptがプログラマーを信用して型を推論しているパターン
getUserTypeでは引数anyに対してユーザーが定義した型を推論されている
その中核にあるのは関数の戻り値に 引数 is Type と記述しbooleanを返している関数
これを ユーザー定義 guard types という
ここのポイントはTypeScriptがプログラマーを信用して型を推論していること
type User = { gender: string; [k: string]: any }
type UserA = User & { name: 'hoge' }
type UserB = User & { age: 1 }
function isUserA(user: UserA | UserB): user is UserA {
return user.name !== undefined
}
function isUserB(user: UserA | UserB): user is UserB {
return user.age !== undefined
}
function getUserType(user: any) {
const u0 = user // any
if (isUserA(user)) {
const u1 = user // UserA
return 'A'
}
if (isUserB(user)) {
const u2 = user // UserB
return 'B'
}
return 'unkown'
}
const x = getUserType({name: 'aaa'}) // 'A' | 'B' | 'unkown'よく利用するfilterは型を絞り込むことができないけどユーザー定義ガード節を利用することで可能になる
type User = { name: string }
type UserA = User & { gender: 'male' | 'female' | 'other'}
type UserB = User & { graduate: string }
const users: (UserA | UserB)[] = [
{name: 'Taro', gender: 'male'},
{name: 'Hanako', graduate: 'Tokyo'},
]
const filteredUsers = users.filter(user => 'generate' in user) // (UserA | UserB)[] と推論されてるここにユーザー定義ガード節を利用した関数を併用すると
function filterUser(user: UserA | UserB): user is UserB {
return 'graduate' in user
}
const filteredUsers = users.filter(filterUser) // UserB[] と推論される
// 匿名関数を使ってこうも書ける
const filteredUsers = users.filter(
(user: UserA | UserB): user is UserB => 'graduate' in user
)TypeScriptの型推論
- TypeScriptは変数に型を必ずしも付与する必要はない
- 代入される値から良しなに型を推論してくれるため
- letとconstの変数は推論の挙動が異なるので注意
- constはLiteral Typeになる(ゆえにに再代入ができない)
const hoge = 'Taro'; // hogeの型は'Taro'という文字列リテラルとして推測される・しかしconstで定義した変数をletの変数に代入するとLiteral Typesがなくなる
const hoge = 0 // 0型
const hoge2 = 'Taro' as 'Taro' // 明示的にアノテーションを付けると再代入でもLiteral Typesを維持してくれる
let fuga = hoge // number型になる
let fuga2 = hoge2 // Taro型・Array型とTuple型の推論はアノテーションを付けなければ良しなに推論してくれる
// Array
const arr = [0, "1"] // (number | string)[]]
const arr2 = [0 as 0, "1" as "1"] // (0 | "1")[]
// Tuple
const tuple1 = [false, 1, "2"] as [boolean, number, string]
tuple1.push(false) // OK
tuple1.push(true) // NG: 2番目はnumber型なので・Object型のプロパティは再代入できる。プロパティをLiteral Typesとして認識させるためにはアサーションを使う
const obj = {
foo: boolean,
bar: false as false
}
obj["foo"] = true // ok
obj["bar"] = true // error ・関数の戻り値も推論が効く。returnする型がわかりきっている場合は定義してあげた方がバグを生まない安全設計になる。
一方で、if文で分岐が複数あり複数の型を返す可能性がある場合は良しなに推論してUnion Typesで型推論してくれる
function hoge(score: number) {
if (score > 10) return null
if (score < 5) return "hoge"
return score
}
// 推論結果: function hoge(score: number): number | "hoge" | nullPromiseの型推論はresolveに型を付けることで安全設計になる
- resolveの型の付け方は2つある(どちらもresolveにstring以外が入るとコンパイルエラー)
// 関数の戻り値型にアノテーション付けるパターン
function hoge: Promise<string> {
return new Promise(resolve => {
resolve("hoge")
})
}
// Promiseのインスタンス作成時に型を付けるパターン
function hoge {
return new Promise<string>(resolve => {
resolve("hoge")
})
}・async関数はreturnされる型を良しなに推論
// async自体がPromiseを返すのでPromise<string>
async function hoge() {
const message = await fuga() // messageにはstringが入ってくる想定
return message
}・importも定義元の型を推論してくれる(ただしrequireはしない)
// test.ts
export const value = 10
-----
import { value } from "./test"
const v1 = value // v1: 10- jsonは型を推論してくれるので便利
ただし、jsonファイルを外部モジュールとしてインポートするにはtsconfig.jsonのresovleJsonModuleとesModuleInteropをtureにする
- jsonは型を推論してくれるので便利
TypeScriptの基礎
- 関数の 引数 には型を付けましょう
- jsは文字列を暗黙的に数値に変換してしまう。意図しない不具合を避けるために型を定義する
- 関数の 戻り値 は型推論が効くのでbetter
- null型 / undefined型という名前の型がそれぞれ存在する(単体では役に立たない)
- object型はブレースを使って定義するとエラーを吐かないので注意
let objectBrace: {}
let objectType: object
objectBrace = true // エラーにならない
objectType = true・複数の型を1つに結合(Intersection Types: &)
type Dog = {
bark: () => void
}
type Bird = {
fly: () => void
}
type Kimera = Dog & Bird // barkとflyの2つを持つ型・複数の型のうちどれか1つの型に適合する(Union Types: |)
let value: boolean | string
value = false
value = "1"
value = 1 // Error・文字列リテラルを型にできる(String Literal Types)
これと同じ要領で数字リテラルやBooleanリテラルもある
let taro: 'Taro'
taro = 'Taro'
taro = 'Taro1' // Error
let zero: 0
zero = 0
zero = 1 // Error・typeofで宣言済みの変数の型を取得
let myObject = { foo: "foo" }
let anotherObject: typeof myObject = { foo: "" } // myObjectの型を取得して定義に利用している・keyofでオブジェクトのプロパティ名を取得
type SomeType = {
foo: string
bar: string
}
let somekey: keyof SomeType // let someKey: "foo" | "bar"・keyofとtypeofの併用でオブジェクトのキーを型として定義できる
const myObject = {
foo: 'FOO'
bar: 'BAR'
}
let myObjectKey: keyof typeof myObject
myObjectKey = "foo"
myObjectKey = "far" // Error・キャストは2種類の記述方法(<>とas)
let someValue: any = "this is a string"
let length: number = (<string>someValue).length
let length: number = (someValue as string).length- クラス
- メンバー修飾子はprivateやpublic以外でいうとprotectedがある
- enumは数値も文字列も両方定義できる
- open endedに準拠しているので同じenumのTypeがあったら自動でマージしてくれる(ただし文字列列挙型に限る)
type Hoge {
Fuga = "fuga"
}
type Hoge {
Foo = "foo"
}
// HogeはFugaとFooを持つ開発環境と設定
TypeScriptのセットアップ操作を通じ的な設定とその意味について解説している
tsconfig.jsonの項目は多く初見では理解が大変なので遭遇したタイミングで立ち戻ってくるのが良い
- tscコマンド
tsファイルからjsファイルをビルドするコマンド
コンパイルの設定はtsconfig.jsonにて定義 - tsconfig.json
- target: どのバージョンのjsとして出力するか
- 簡単に言うと古いバージョンにするとオブジェクトや関数が使えないということ
- module: どのモジュールパターンで出力するか
- commonjs: サーバー側(Node.js)利用想定
- amd: ブラウザ側利用
- umd: commonjsとamdの両方に対応
- strict: true
- noImplicityanyやnoimplicitthisなどの基本的な型チェックを 一括 で有効化
- outdir
- コンパイルしたjsファイルの出力先ディレクトリ
- 明記しない場合はtsファイルと同じ階層にjsファイルがビルドされる
- declaration: true
- 型宣言ファイル(xxx.d.ts)を出力
- 通常の開発で有効にするケースは少ない
- 利用シーンとしてはライブラリを自作やProject Referenceを利用する場合
- exclude: ビルドから除外するファイル・ディレクトリを指定
- include: excludeの反対。excludeより弱い
- files: ビルドに含むファイル。excludeより強い
- extends
- tsconfig.jsonを継承できる
- チームで共通する設定がある時に使うイメージ
- target: どのバージョンのjsとして出力するか
- Build Mode
- tscコマンドのbオプション
- どのtsconfig.jsonを使うかを明示できる
# src/tsconfig.jsonを利用する
tsc -b src